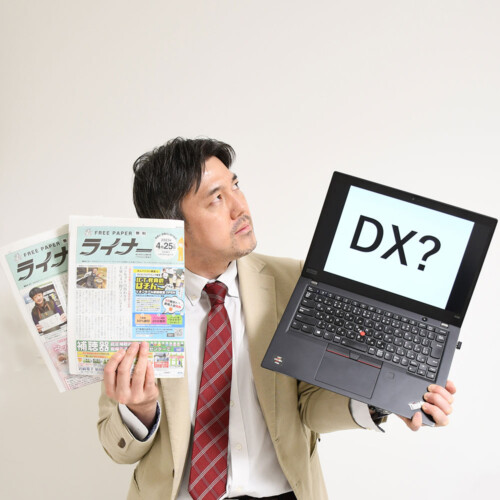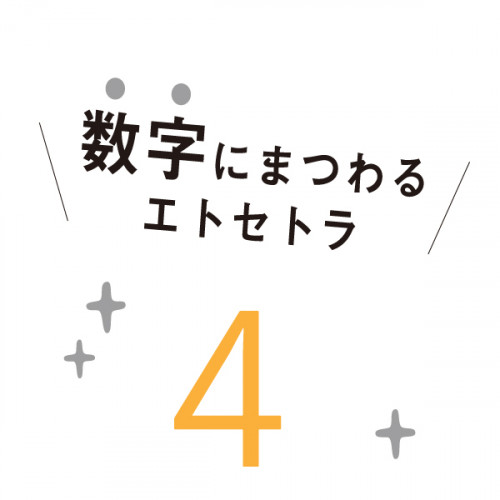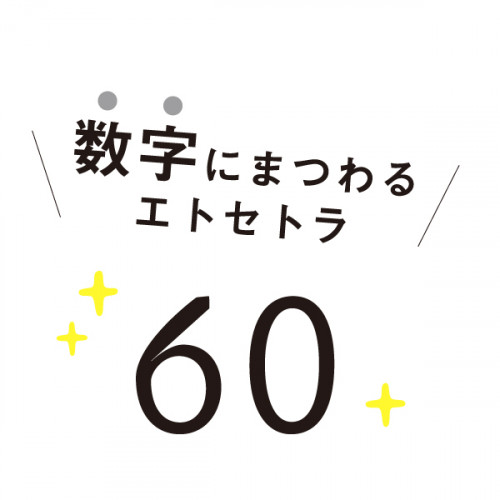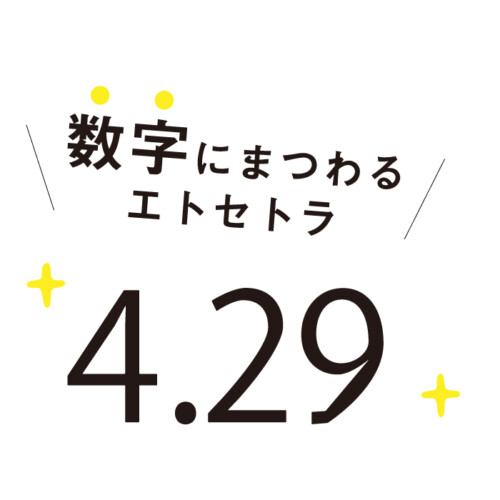2500年前の哲学に学ぶ、「聴くこと」の難しさ
本やラジオ、YouTubeで仏教の哲学に触れるのが最近のマイブーム。しかし、知れば知るほど反省することが増えていく。これは、私自身の懺悔の話です。
私たちの仕事は、広告や記事を通じて読者に情報を届けること。伝えることの難しさは日々実感していますが、最近はさらに「聴くこと」の難しさを痛感しています。取材や広告の打ち合わせでは、相手の想いが明確なことが多く、伝えたいこともはっきりしていますが、一方で家族のような距離の近い関係ほど、自分の思い込みが邪魔をしてしまうことがあります。
例えば小学3年生の娘が学校での失敗談を話してくれたとき、その受け止め方は本当に正しかったのか。親の目線で「こうあるべき」と考え正しさを押し付け、「普通なら」、「前にも言ったけど」、「何でわからない?」と、つい先に言葉が出てしまう。もし娘の気持ちや置かれている状況をもっと聴けていたら、返す言葉も変わっていたのかもしれません。娘はきっと「普通ってなんだよ!」と思っているでしょう。
仏教では、こうした考えのこだわりや執着、つまり自我を「煩悩」と呼ぶそうです。人間関係には、公私を問わず立場の違いがあります。売り手と買い手、上司と部下、そして親と子など。特に自分が優位な立場にいると、自我を押し通しやすくなり、「聴く」より「伝える」が優先されるような場面も少なくありません。相手に伝えたつもりがうまく伝わらなかったり、逆に相手の言葉を正しく受け取れなかったりすることがありますが、もしかすると「こうだろう」という自分の思い込みに原因があるのかもしれません。
腑に落ちないことも時間が経って冷静になると、自分の中に原因があると気付くことも多々・・・。あぁ、またやってしまった、と反省。「分別のある人」と聞くと良いことのように思えますが、仏教では「無分別」を説くそうです。自他を区別せず、平等に見ること。自分の価値観を物差しにして、あたかも分別があるかのように調子よく語る。その傲慢さに気付き、また反省。
日々、己の未熟さを痛感し、慚愧の念に堪えませんが、煩悩が以前よりはっきり見えるようになったことを「聴くこと」への第一歩と前向きに捉えています。聴く姿勢も、腕や脚を組むなど、無意識の態度が相手に与える影響にも気を配りながら。
最後に、「聴す」、この読み方をご存じでしょうか。江戸時代以前は「ゆるす」と読んだそうです。「聴くことは、許すこと」。とても感慨深く、そして難しい。
もし、私から煩悩がにじみ出ていると感じたら、どうか許してほしい…そんな煩悩を抱く自分に、また反省。
広告部 月居